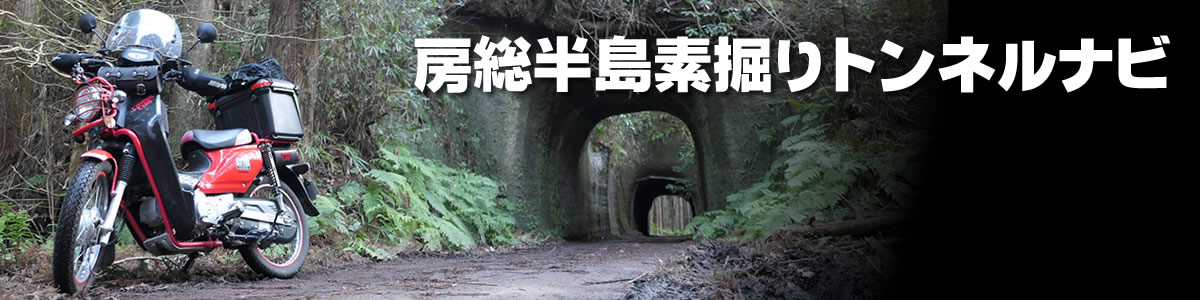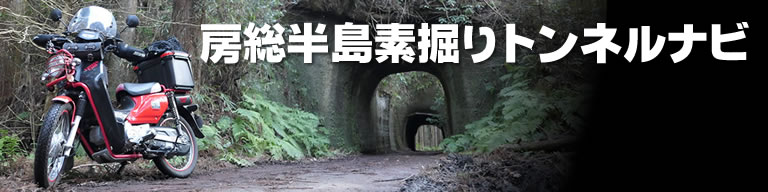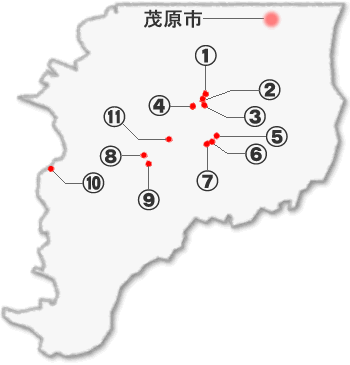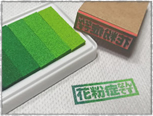【追記(2022年3月13日)】もともと「<仮名>小田代素掘りトンネル2号」としていましたが、大多喜町の資料「大多喜町トンネル長寿命化修繕計画(PDF)」内に「清水代トンネル」との記述を確認したため当サイトでもこの名称を利用いたします。
小田代素掘りトンネル1号(仮名)からさらに少し先へ南下した右側に突如現れる素掘りトンネル。林道の分岐点に作られた短いトンネルだが、内壁には斜めに走る地層がくっきりと見られ、西側の大きく地層が歪んだ出口など、様々な目の錯覚を生み出す世にも奇妙なトンネル。
トンネルの幅は狭く軽でギリギリかという感じだが、車のタイヤ痕がしっかり残っていた。慣れていない人が入れば擦る可能性大。西側の出口の先はしばらく下り坂が続く。平らなところでUターンをと思うと少し先まで行かないといけないので、不安な人は手前で一度バイクを停車し、トンネル通過後の道の状況も確認したほうが安全。道はさほど悪くないものの落ち葉などもたくさんたまっている(道の状況は動画を確認のこと)。地図によると奥養老バンガロー村につながる道のようだ。なお南側に伸びる道は最後行き止まりとなる。
【追記(2020/09/15)】 2019年秋台風による倒木・崖崩れでトンネル東側開口部につながる道が通行できなくなっています/2020年8月時点でアクセス可能なルートをまとめました
概要
| 住所 | 千葉県夷隅郡大多喜町小田代 |
| 全長 | 未確認 |
| 建設時期 | 未確認 |
| 駐車場 | ─ |
| トイレ | ─ |
| マップコード | 309 859 878*40 |
アクセス
<車・バイクの場合>
養老渓谷温泉から向山トンネルをくぐり奥養老バンガローに向かう道の途中で林道に入る/車の場合、養老渓谷温泉の有料駐車場に車を停め、徒歩で訪れることも可能
<公共交通機関の場合>
養老渓谷温泉の中心地から1.5キロほど(徒歩23分程)/小湊鉄道養老渓谷駅から路線バス(養01「栗又・ごりやくの湯行き」)乗車5分、弘文洞入口バス停で下車すればそこから徒歩21分程
関連記事リンク
- 何度でも訪れたい日本の風景「【千葉】時空が歪んだような素掘りのトンネル」・・・房総半島の素掘りトンネルを多数踏破している方のレポート。
- Webでも考える人「●第7章 世にも奇妙な素掘りトンネル」・・・ここ以外の素掘りトンネルもまわっており、「トンネルを掘った人たちはどこへ行ったのか」など非常に読みごたえのある文章。
動画
▼小田代素掘りトンネル2号(?)─バイク(2分07秒)/YouTubeで見る
訪問レポート
養老渓谷温泉のメインストリートから"二階建てトンネル"こと向山トンネルを抜け、さらに小田代素掘りトンネル1号を通過してすぐ、右手にトンネル・・・というか洞穴のような縦長の長方形の入り口を見つけて急停車。
もしやこれもトンネルか???
覗き込むと、奥にしっかり出口が見える。
トンネルだ!
内壁の地層のせいか、なぜか奥の出口にむけてトンネルの内径が急激に狭まっているように見える。単なる目の錯覚なんだけど。
照明もなく、開口部のコンクリ補強などもなく、完全なる素の素掘りトンネルだ。
入ってみると、外から見た時の印象よりは幅があった。小型バイクはもちろん、大型バイクでも十分入っていける幅だった。
というか、ネットで訪れた人のブログ記事を見ていたら、ここに車で突っ込んでいる人もいる。車幅ぎりぎりだと思うんだけど。擦って大変なことにならないのか、そもそもそんなこと気にしないオフロード好きの人なのだろうか。
内壁はこんな感じで、明らかに構成物が異なる地層が重なっている。地質に詳しい人と一緒なら、どういう経過でこのようにごつごつした部分が顔をのぞかせているのかなど解説してくれるのだろう。
このあたり一帯は、海底に蓄積した泥や砂の層が隆起して作られた丘陵地帯だそう。割と幅狭めのミルフィーユ状になっているのはそういうこととも関係あるのだろうか。
ただこのトンネル、感動ポイントはこの先だ。
出口の先の道が見えないので、流石にいきなり「崖」ということはないと思いつつ、おそらく下り坂になっているのだろうとスピードを落として慎重に出ていき、バイクを停めて振り返ってびっくり。
わお!まさに"割れ目"!
トンネル上部からぎゅっと何かで押されて潰れたかのような歪みがなんともいえない不気味かつ迫力ある風景を作り出している。
見れば見るほど「股」のようにも見えてくるのは、上部の歪みに加えトンネル開口部の両サイドが丸みを帯びているせいだろう。これはトンネルを作った時からそうだったのか、それとも後に風化してこうなったのか、あるいはもともと自然の造形でこうなっていたところをトンネルにしたのか。
詳しい人がいたら聞いてみたいことだらけだ。
ちなみにトンネル上はこんな感じで、それほど高低差がある場所なわけでもなし。これは房総半島の素掘りトンネル全般に共通することで、トンネルがなくてもアップダウンの道で軽く越えられる程度の場所にもかかわらず、トンネルを掘ってショートカットしている。
掘りやすい地層で、トンネル作りが「世紀の大事業」というほどの難工事ではなかったからなのだろうが、そうは言ってもこれだけ掘り進むのは容易なことではない。そしてこのトンネルの先にその昔、多くの人が住む集落があったとは思えない。謎だ。
記念撮影。
後で気付いたのだが、素掘りトンネル前で記念写真を撮る時には、ちゃんとそこがトンネルだとわかるよう、反対側の出口も写り込む角度で撮影すべきだ。ここはトンネルの先が下り坂なので、三脚も必要だった。ひとりで回る人で記念撮影したいなら忘れず持参すべき。
トンネル内から見た東側の出口。幅は狭いが、実はかなり縦長に掘られていることがわかるだろう。なぜこの高さが必要だったのだろうか。
車はもちろん、自分以外誰もいない場所なので、遠慮なくこんな記念撮影もできる。
どう撮るべきだったのか、なかなか難しい。
ちなみにこのトンネルの先(西に伸びる林道)、しばらく緩やかな下り坂道になっていて、途中からこんな感じの道になる。地図によると、ずっとまっすぐ進めば奥養老バンガロー村近くに出られるようなのだが、時間もなかったので引き返してきた。